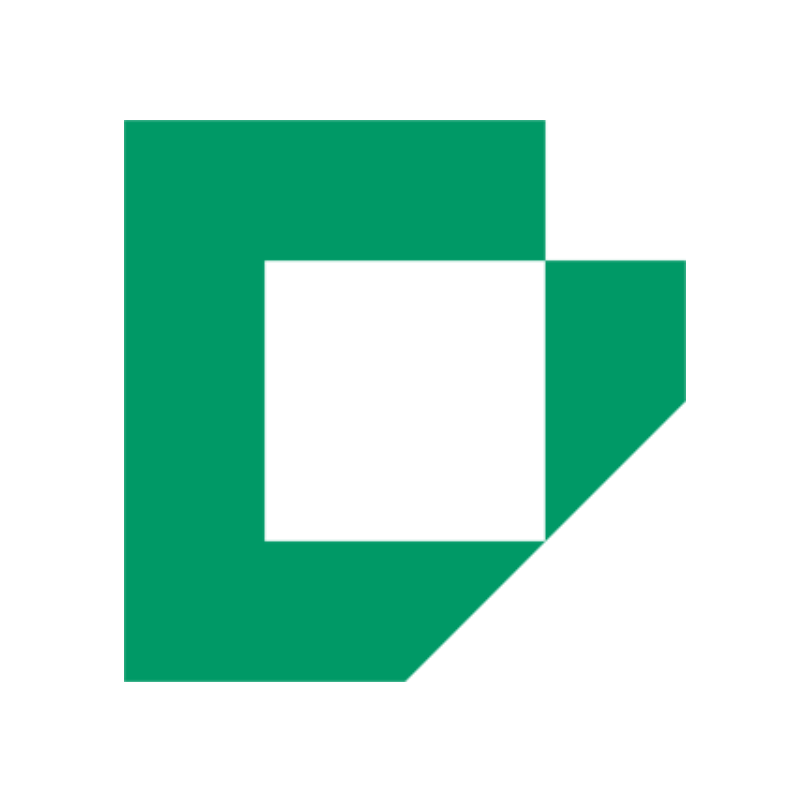マンガ家になるには?夢を叶えるための完全ガイド
2025/7/22
目次
・マンガ家になるにはどうすればいい?
・どうやってセンスを磨き、どうやって努力をすればいい?
・そもそもマンガ家ってどんな仕事?
マンガ家になりたいけれど、何をすればいいの? と迷っているあなたへ。掲載&受賞実績3,700作品以上を誇る専門学校日本デザイナー学院が、皆さんのギモンに徹底回答。本校の講師でマンガ家/イラストレーターとしても活躍する太田和敏先生の監修のもと、これからマンガ家を目指して羽ばたいていく皆さんの羅針盤となる記事を目指しました。ぜひお役立てください!
マンガ家とは? 仕事内容とその魅力
マンガ家ってどんな仕事?
マンガ家は、自分で考えたストーリーやアイデアなどをマンガというかたちで表現し、読者に届ける職業です。あなたの想像力を自由に発揮し、多くの人の心に届けられる、とてもクリエイティブで夢のあるお仕事です。
マンガ家が描いた作品は、雑誌やWebなどに連載されるほか、単行本として出版されるのが一般的です。この連載時の原稿料や、単行本の印税、アニメやグッズなどで二次使用されるときの原作使用料やロイヤルティなどが、マンガ家の収入源ということになります(収入源については、後の章で詳しく解説しています)。
原作から作画までを一人でこなす作家もいれば、シナリオや作画を分業するケースもあります。日常的な業務には、ネーム作成(コマ割り・セリフの構成)、作画作業、編集者との打ち合わせ、アシスタントへの指示、締切管理などが含まれます。
日本のMANGAが世界から注目されている理由
言わずと知れた人気マンガ『ONE PIECE』は、海外でも60ヵ国以上で出版されており、累計発行部数1億部と大ヒットしています。
世界から愛され、注目されている日本のマンガ。その人気のヒミツのひとつは、イギリスのガーディアン紙の記事によれば、NetflixやAmazonプライムビデオなどの動画配信プラットフォームが普及したことにより、日本のアニメが世界中の人にとって身近なものになった、という点が挙げられるのだそうです。
サブスクで日本のアニメを見て好きになり、続きを読みたい、より深く作品を理解したい、または大好きな作品をコレクションしたいという動機から、日本のマンガ作品を購入する人が海外でも増えているのです。
古くは絵巻物や鳥獣戯画にもルーツがあるとされる、日本のマンガ(『ONE PIECE』には落語からヒントを得たエピソードも出てくることも有名です)。その面白さと文化的ユニークさが、サブスクという最新ムーブメントをきっかけに世界中で再注目されているのです。
マンガ家の仕事内容は?
プロット(構成・あらすじ)の作成
プロットは、物語の骨格を作る重要なステップです。どんなテーマでどんなキャラクターが登場し、どのような事件や対立、解決が起こるかなどを簡潔にまとめます。これによって物語の流れや構造を事前に把握することができ、制作全体の指針となります。
長編マンガの場合、たいていはシリーズ全体の長期的なプロット、1話単位の短いプロットの両方を作成します。編集者との打ち合わせでは、まずこのプロットを提示して内容の方向性や構成の意図を伝えるケースが多いです。読者を惹きつけるいい作品をつくるには、まずはこのプロットを魅力的なものに練り上げていくことが重要になります。
ネーム・絵コンテの制作
ネームとはいわばマンガの設計図。コマ割りとセリフ、キャラの配置を簡易的な絵で描いたものです。実際にページをめくる読者の目線やテンポを意識しながら、構成・演出を調整する大事な作業です。
セリフの量や、コマの大きさ、キャラクターの表情や動きなどを、読み手への伝わり方も考えながら作るため、最も想像力を使う工程といえるかもしれません。
編集者との打ち合わせでも、特にこのネームを念入りに揉む場合が多いです。『ドラゴンボール』や『ONE PIECE』といった傑作でさえ、漫画家一人だけの独創でつくられることはまれで、編集者とのディスカッションを重ねながらネームに修正を加え、よりよいものにしていきます。そのままマンガの面白さに直結するネームは、非常に重要な工程のひとつです。
下描きの作成
ネームをもとに、実際の原稿サイズでキャラクターや背景のラフスケッチを描いていくのが下描きの工程です。線の強弱やパース(遠近法)も意識しながら、人物のポーズ、表情、衣装、背景の構図などをなるべく正確に描写し、後のペン入れの土台を形成します。
この下描きを丁寧に仕上げるほど後の工程がスムーズになるため、作画のバランスなど細かい部分まで詰めながら時間をかける作家が多いです。デジタル作画の場合も、この工程でレイヤーを使いながら構図を確認し、細部を整えていきます。
ペン入れ(本番の線画作業)
ペン入れは、下描きをもとに清書を行う工程で、作品の完成度が大きく左右される重要な作業です。主線を美しく整え、キャラクターの輪郭や表情、背景のディティールなどを丁寧に描き起こします。
紙にインクで描くアナログ作画では、Gペンや丸ペン、筆ペンなどの道具を使い、ミスが許されない緊張感の中で線を引きます。デジタル作画ではタブレットと作画ソフトを用うため、紙よりも効率よく作業を進められる部分も多いですが、線の美しさや強弱といった作画技術が求められる点ではアナログと変わりません。
絵の表現力が試されるペン入れの技術を高めるには、練習と経験の積み重ねが必要になります。
仕上げ(トーン・ベタ・効果など)
仕上げの工程では、キャラクターや背景に影をつける「ベタ塗り」、グレーの薄い影や模様などを表現する「スクリーントーン」の貼り付け、「集中線」や「効果線」といった演出を加えるなどして、マンガに奥行きや迫力を加えていきます。
この仕上げを丁寧に施すことにより、キャラクターの感情やシーンの雰囲気をより細やかに、リアルに表現できます。アシスタントが担当することも多い工程ですが、完成後は作家自身が全体を最終チェックし、必要に応じて修正を行ったら、晴れて原稿の完成です。
マンガ家デビューへの道のりは? 3つの王道ルートを紹介
プロのマンガ家になるためには、具体的にどのようなアクションを起こし、どのような道のりを歩めばいいのでしょうか? 代表的な3つのルートをご紹介します。
新人賞に応募する(投稿)
マンガ家を目指す最も王道のルートといえば、出版社主催の新人賞に応募することです。集英社の「手塚賞」「赤塚賞」、小学館の「新人コミック大賞」、講談社の「新人漫画大賞」などが有名ですが、そのほかの出版社やWeb媒体などが主催する賞や、毎月開催されている小規模なマンガ賞(たとえばJUMP新世界漫画賞など)も数多くあります。
■主な新人賞
手塚賞・赤塚賞(集英社)
新人コミック大賞(小学館)
新人漫画大賞(講談社)
受賞すればマンガ家としてデビューできるほか、たいていの新人賞には賞金も用意されています。受賞後には編集部内での掲載会議があり、それが通れば晴れて連載スタート。仮に落ちてしまったとしても、人に読んでもらう前提で本気で作品をつくり上げるいい機会になり、またプロのマンガ家や編集者から批評をもらえる可能性もあるため、自分のマンガを見直す貴重なきっかけを得られます。
マンガ家を目指すなら、こういった新人賞の情報を確認し、応募する先を絞り込んでおきましょう。
出版社に持ち込む
出版社に作品を持ち込むのもひとつの方法です。事前にアポを取っておくことで、編集者があなたの作品をその場で確認してくれることがあります。もし光るものがあれば、作品についてアドバイスをくれたり、修正して再度持ち込むように言ってくれるかもしれません。一概にデビューにつながるとは限りませんが、自分のマンガを見てもらい、プロの目からアドバイスをもらうチャンスになります。
ただし持ち込みからそのままデビューというケースはまれで、たいていは、その出版社が主催している新人賞に応募するようにアドバイスされます。もしあなたが期待の “金の卵” と期待されれば、担当編集者が受賞に向けて二人三脚で作品づくりをサポートしてくれるケースもあります。
ネットに掲載する
繰り返しになりますが、近年はネットに掲載した作品からデビューにつながるケースも増えています。
SNSやマンガの投稿サイトなどに作品を掲載し、ファンを獲得する、高い評価を得るなどの反響が得られれば、出版社から直接アプローチをかけられる可能性もあるかもしれません。SNS発信のマンガが書籍化するパターンは最近では珍しくなくなってきており、ネット経由でのマンガ家デビューという道筋も1つの手段として念頭に置いておきましょう。
本記事監修の太田和敏先生によれば、特にX(旧Twitter)は画像を4枚、つまり4ページぶんを一度に見せられるため、マンガに適したSNSなのだそうです。
マンガ家になるには、どんな努力をしたらいい?
マンガ家になるには、キャラクターや背景を描く画力に加えて、感情表現やアクションを魅力的に見せる表現力、読者をひきつけるストーリー構成力やセリフ回しなど、総合的なクリエイティビティが問われます。
そのためにはさまざまなものをインプットしてセンスや知識を磨くとともに、デッサンやキャラクターデザインをはじめとするトレーニングを適切な方法で積み重ねることが大切です。
ここではマンガ家の夢を叶えるためにやっておくべき、有効な方法をご紹介します。
映画を観る
ストーリーの運び方、画面の見せ方・構図などのセンスを養うには、さまざまな作品を鑑賞し、その良さや面白さをインプットすることが大切です。
そのインプット源として特に太田先生が勧めているのは「映画」です。
「マンガ家を目指しているんだから、マンガをたくさん読むべきじゃないの?」と思われるかもしれませんが、じつはそれだけでは十分ではありません。たしかにマンガをたくさん読み、マンガならではの表現方法や表現マナーといったものを学ぶのは大切な勉強です。しかしマンガ「だけ」をインプット源としてしまうと、既存のマンガ作品と似たようなありきたりな表現になってしまいがちなのです。
その点、映画はマンガと違って実写であり、監督によって撮り方や表現の幅も広いので、いい意味で「マンガらしくない」表現方法をインプットできます。また映画は動きのある「動画」なので、そのぶん情報量が多く、ひとつのシーンをさまざまな角度から、さまざまな切り取り方で解釈できる点も魅力のひとつです。
さまざまなことを「実体験」する
遊びも含めていろんなことにチャレンジし、「実体験」を積むのもマンガ家の勉強のひとつです。
マンガはフィクションの世界ですが、その中に描かれる感情や動き、ものの質感などは「リアル」なものです。たとえデフォルメされた作風だったとしても、絵や表現がリアルであるほど、読者はその作品に「本物らしさ」を感じ、心をひきつけられたり揺さぶられたりします。
リアルな世界を描くためには、マンガや映像作品などのフィクションからだけでなく、本物の「実体験」を積み、現実世界の質感や理(ことわり)を身をもって知ることが大切です。
たとえば監修の太田先生は、20年ほど前、オーストラリアで本物の銃の射撃を体験したことがあるそうです。薬きょうの飛び方、熱さ、反動、音など、実際の拳銃の動き方や手ごたえは、マンガや映画などで見てイメージしていたものと全く異なっていたことに驚いたのだそうです。
本物の銃を撃ったことがあるか、そうでないか。銃を撃つシーンを描くとき、この経験があるかないかで、描かれるシーンのリアリティは大きく変わってくるはずです。
ちなみに太田先生によると、拳銃を撃ったときのマンガの擬音といえば「バキューン」がおなじみですが、『ドラゴンボール』などで知られる鳥山明先生は「パン」という擬音を使うことが多いのだそうです。この「パン」は実際の銃声にニュアンスが近いため、鳥山先生もどこかで拳銃を撃つ体験をしたことがあるか、もしくは実際の拳銃の音をしっかり観察して再現したのではないかーーと太田先生は推察しています。
射撃という非日常的な経験に限りません。自動車の運転。スポーツ。キャンプ。恋愛。友達と遊んだりケンカしたりといった人生経験。あなたのすべての「実体験」がマンガの糧になります。マンガの世界はフィクションですが、その素材は、あなたがどこかで見聞きしたこと、感じたことといった「記憶」でできているからです。
少し話が逸れますが、「計画的偶然性理論」という言葉があります。これは人生の8割が偶然によって左右されるという前提のもと、だからこそ、良い偶然を “計画的に” 起こす方法を考えるものです。簡単に言うと、「いい偶然」に出会うためにはさまざまなことに好奇心をもってチャレンジし、ときには失敗してもあきらめずに続けてみることで道が開けるーーというのが、計画的偶然性理論の骨子です。
■計画的偶発性を起こす行動特性
好奇心(Curiosity):新しいことに興味を持ち続ける
持続性(Persistence):失敗してもあきらめずに努力する
楽観性(Optimism):何事もポジティブに考える
柔軟性(Flexibility):こだわりすぎずに柔軟な姿勢をとる
冒険心(Risk Taking):結果がわからなくても挑戦する
(出典)RGF|計画的偶発性理論とは?クランボルツ教授に学ぶキャリアデザイン
作品づくりについてもまったく同じことが言えるかもしれません。作品のアイデアや素材となる「いい実経験」に偶然出会うには、偏見をもたずにさまざまなことに興味をもち、「何事もまずはやってみる」という精神をもつことが大切なのです。
締め切りを意識して、描きまくる
マンガ家を目指すのなら、「マンガを描く」という行動を習慣化するのがポイントです。毎日マンガを当たり前のように描き、休まずに継続する力を養うことが、マンガ家になるための地盤となります。「気が向いたときにだけ描く」「今日は気分が乗らないから描かない」といったスタイルでは、なかなか実力が伸びず、作品の仕上がりも遅くなるため、デビューが遠のいてしまうかもしれません。
太田先生は、アマチュア時代のうちから自分で〆切を設定し、そこに向けて作品を仕上げていくことをすすめています。〆切があることで必然的に描く習慣が身につきますし、無理やりにでも何かアウトプットしているうちに、その中で何か発見があったり、思わぬ成長を実感できることもあるはずです。
特に新人賞の〆切は、「過ぎると応募できなくなる」という究極の強制力をもっています。〆切までに作品を仕上げるトレーニング、という意味でも、新人賞への応募は有効な手段と言えるでしょう。
太田先生のマイルールとしては、「締切の3日前」までに作品を仕上げることを自分に課しているとのこと。提出後に万が一編集部から修正の依頼が来ても、3日も余裕があれば対応できるからです。
プロデビューに備えたトレーニングの一環として、締め切りを明確にすること、その3日前を目指して作品を仕上げていくことを、ストイックに続けてみてはいかがでしょうか。
専門学校で学ぶ
専門学校は、マンガ家になるための技術や知識を体系的に学べる場です。ここでは、私たち専門学校日本デザイナー学院についてご紹介しましょう。
本校のカリキュラムには、デッサン・デジタル作画・ネーム制作・ストーリー演出・キャラクターデザイン・背景描写など、マンガ家になるために必要なすべてのスキルを磨く授業が組み込まれており、作品制作などの「実習」を通じてそれを身につけていきます。
またプロのマンガ家や編集者が講師を務めるので、業界内部のリアルな動向や事情、それを踏まえた実用的なアドバイスを受けることができます。また出版社による作品講評会、編集者とのマッチングイベントなど、デビューの足がかりとなるイベントも用意しています。何より、同じ志をもった仲間たちと切磋琢磨し、励まし合いながら成長できるのが、学校という環境ならではの魅力ではないでしょうか。
マンガ家のアシスタントになるには?
アシスタントはプロへの近道
マンガ家のアシスタントは、背景描写や効果線の作画、ベタ塗り、トーン貼り、資料集めなどを担当する、作品制作の重要なサポート役です。特に連載作家は締切に追われることが多いため、アシスタントの存在は欠かせません。
アシスタントの仕事を通じて、現場の作業スピードやプロの技術、編集とのやり取りなどを学ぶことができます。プロの技術を間近で見られるだけでなく、作品作りに対する姿勢や締切管理の感覚など、自分がマンガ家を目指すうえで非常に大きな経験となります。
どうやってアシスタントになる?
アシスタントの求人は、出版社の編集部やマンガ雑誌の公式サイト、SNS(XやInstagramなど)で公募されていることがあります。応募時には、ポートフォリオ(過去の作画サンプル)が求められることが多く、背景・小物・人物など幅広い作画ができると有利です。近年ではリモートで作業できる環境も整いつつあり、地方在住でもチャンスを掴める可能性が広がっています。アシスタントとして数年経験を積みながら、デビュー作を制作するというルートは、多くのマンガ家がたどってきた実践的な方法です。
マンガ家に必要な資格とは? – 基本的に必要なし
マンガ家として活動するために、特定の資格は必要ありません。マンガ家とは「作品を描いて売る人」なので、作品が面白くファンがつけば、プロのマンガ家として活動することができます。
直接的な必須資格はなありませんが、強いて言うなら、作画やクリエイティブツールに関する民間資格は役に立つ可能性があるかもしれません。たとえば「色彩検定」「CGクリエイター検定」「Photoshopクリエイター能力認定試験」などの資格は、デジタルマンガをつくるうえでの知識として役立つ場合があります。将来的にアシスタントとチームを組んでの仕事に備える意味では、コミュニケーション力やマネジメント力に関する勉強もしておいて損はないでしょう。ただし最も優先すべきは、実際の作品制作と発信であることは変わりません。
マンガ家の収入源は?
少し現実的な話として、マンガ家の収入源についてもお話しておきましょう。
原稿料と印税が基本的な収入
マンガ家の主な収入源は「原稿料」と「印税」です。
「原稿料」とは、雑誌やWebメディアに載る連載や読み切り作品に対して支払われる報酬のことで、1ページあたり数千円〜数万円と幅があります。新人作家の場合は低めの単価からスタートし、人気や実績に応じて上がっていきます。
「印税」は、単行本の売上に応じて支払われる報酬で、一般的には定価の8〜10%ほどが作家に入る仕組みです。売れ行きによっては1巻につき数百万円〜数千万円の収入になることもあり、人気作家になるほど大きな収益源となります。
二次利用・グッズ展開・映像化による収益
近年では、マンガ作品の二次利用による収益も注目されています。アニメ化・映画化・ドラマ化などの映像作品化にともない、契約内容に応じて原作使用料(ロイヤリティ)が著者に支払われます。
またキャラクターグッズ、フィギュア、コラボ商品などのグッズ展開からも、ロイヤリティというかたちで収入が得られます。近年では企業とのタイアップ企画や広告マンガ、デジタルコンテンツ販売(LINEスタンプなど)などさまざまなコラボの仕方が出てきており、収益化のバリエーションは大きく広がっています。
このように、1つの作品やキャラクターがさまざまなかたちにビジネス展開されることで、収益構造が多様化しているのが現代のマンガ家の特徴です。
Webマンガ・電子書籍・SNSからの収益
紙媒体だけでなく、Webマンガや電子書籍の収益も重要な柱となっています。
Webマンガアプリや電子書籍配信サービスでは、閲覧数に応じた広告収入や閲覧課金が発生し、出版社を介さずに個人で収益を得ることも可能です。またSNSや個人サイトなどにマンガを公開し、グッズ販売やファンからの支援(PixivFANBOXやPatreonなど)によって収入を得ている個人作家もいます。
Webの発展により、出版社に属さない “独立系” のマンガ家でも、活動資金を確保しながら創作活動を続けられる可能性が広がっているのです。また自力で公開した作品が出版社の目に留まりスカウトされる、という新たなデビューの形も生まれてきています。
***
マンガ家になるにはどんなルートがあり、そのためにどんな努力をすべきなのか。この記事を通じて見通しがはっきりしてきたでしょうか。専門学校日本デザイナー学院は、あなたのマンガ家デビューの夢を応援しています!