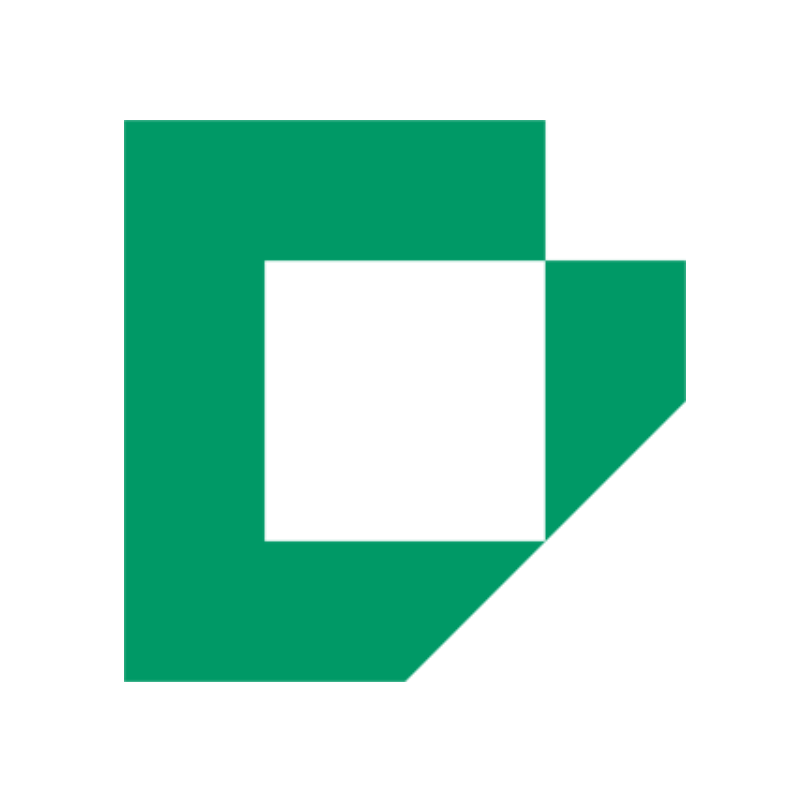アニメーターになるには|未経験からプロになるまでの完全ガイド【2025年最新版】
2025/4/19
目次
「アニメーターになりたい!」と将来の夢を描いている皆さんへ。
・どうやったらアニメーターになれるの?
・そもそもアニメーターってどんな仕事?
・アニメーターになるために、今からやっておくべきことは?
アニメーターを目指すうえで気になるさまざまなギモンに、専門学校日本デザイナー学院がまるっと回答! この記事一本で、アニメーターになるために必要なすべてがわかる! というクオリティを目指して記事をつくりました。
アニメーターを本気で目指している人はもちろん、ちょっと興味がある人や、アニメがただただ好きでその裏側のお仕事を覗いてみたい、という人まで、ぜひ読んでみてくださいね!
アニメーターってどんな仕事?
アニメーターとは、アニメ作品のキャラクターの動きや、背景の動きなどを描くお仕事。いわば「アニメーションに命を吹き込むプロフェッショナル」です。
日本のアニメ作品は、いまや世界中から注目され、高い評価を集めています。日本が世界に誇る「アニメ」という文化を創り上げ、その作品世界を支えるうえで無くてはならないお仕事。それがアニメーターなのです!
この章では、そんなアニメーターという職業の本質と役割について、詳しく解説していきます。
アニメーターには「原画」「動画」の2種類がある!
アニメーターは大きく「原画担当」と「動画担当」に分けられます。
・「原画担当」
アニメーションの「骨」=動きのキーとなるポイントを描く役割。
ベテランが担当。
・「動画担当」
アニメーションの「肉」=原画と原画の間をなめらかに埋めるアニメーションを描く役割。
新人が担当。
「原画担当」は、キャラクターやモノの動きの「キーポイント」を描きます。
キーポイントというのは、「パラパラ漫画が最低限成り立つ点」と言えばわかりやすいでしょうか。アクションが変化するポイントや、表情が移り変わるポイントなど、アニメーションの「骨格」となる部分を描き上げる役割です。
つまりこの「原画」によって映像のベースが決まってしまうため、物語の流れや、キャラクターの感情、監督が目指している演出効果などを正しく理解し、高度に描ききる力が求められます。作品の骨組みを構成する重要なポジションです。
一方、「動画担当」は、「原画担当」が描いた原画と原画の間のコマを描き、滑らかに動かす役割です。つまり「原画担当」がつくった “骨” にきれいに “肉” をつけていくお仕事なので、アニメーションの仕組みを正しく理解し表現する技術、そして効率的な作業スピードも問われるポジションです。
新人はこの「動画担当」からキャリアをスタートするのが一般的で、現場経験を積むことで「原画担当」に昇格していきます。
アニメーターのやりがいと魅力
アニメーターの最大の魅力は、やはり自分が描いたキャラクターがスクリーン上で動き、物語の一部になる喜びではないでしょうか。
アニメのオープニングやエンディングのクレジットに自分の名前が載ったり、SNSでファンから感想をもらったりすると、大きな達成感を得られるはずです。
『進撃の巨人』『SPY×FAMILY』などを手がけた制作会社「WIT STUDIO」のWebサイトでも、アニメーター(原画担当)として活躍する大房彩花さんが、次のように仕事のやりがいを語っています。
質問:仕事のやりがいはなんですか
エンディングのクレジットに自分の名前が入っていると自分も作品の一部になったと感じてとても嬉しくなります。初めてクレジットされた時は家族や友達に名前載ったよと報告したことを今も覚えています。
(出典)WIT STUDIO|社員インタビュー
また映像制作はチームワークでもあります。原画、動画、撮影、演出、音響など、さまざまなスタッフたちと協力してひとつの作品を完成させるプロセスには、アニメータ―ならではのやりがいがあります。
作品ごとに新たな演出方法やテクニックにも挑戦しながら絵のスキルを磨いていくこともでき、あなたの創造性と想像力をぞんぶんに発揮できる職業です。
アニメーターになるための主なルート
アニメーターになるには、具体的にどんな進路に進めばいいのでしょうか? ここでは王道のルートとして、「専門学校に入学→アニメ制作会社に就職」という流れをご紹介します。
ステップ1. 専門学校に通う
アニメーターになるための最初のステップは、専門学校などでアニメーションを学び、スキルを身につけることです。
アニメーターになるには、「絵と絵をつないで動画をつくる」という専門的なスキルが必要になります。この高度なスキルを身につけるには、やはりしっかりとした教育機関に通い、実際にアニメーターとしての実績豊富なプロの講師に教えてもらうのが一番の近道になります。

私たち日本デザイナー学院の総合アニメ・デジタルイラスト科の例では、「アニメーターになる」というあなたの夢を全力でサポートすべく、アニメーション制作の基礎はもちろん、作画の仕方、就活に向けたポートフォリオ(自己PR用の作品集)づくりなどを、実習(作品づくり)を通じて着実に身につけられるカリキュラムをご用意しています。

本学科のカリキュラムは、スタジオジブリのアニメーターも長年務めた舘野仁美さんと、舘野さん率いるササユリ動画研修所が監修しています。
そのほか、アニメやイラストの世界で現役クリエイターとして活躍する講師陣が脇を固め、あなたの成長をサポートします。
アニメやイラストの世界で活躍する現役クリエイターが講師を務めるからこそ、現場のリアルなお話や、アニメーターになるための現実的なアドバイスなど「生きた知恵」を聞くことができ、最短距離で夢の実現を目指すことができます。また業界とのつながりも活かしながら、企業説明会や求人紹介など、就職・キャリアについてもしっかりサポートします。
日本デザイナー学院|総合アニメ・デジタルイラスト科の特徴
・実習メインの授業で、アニメ制作のスキルが身につく
・プロアニメーター養成機関「ササユリ動画研修所」がカリキュラムを監修
・講師は現役クリエイターだから、夢につながる「生きた知恵」を学べる
ステップ2. ポートフォリオをつくる
アニメーターとして就職する、または仕事を得るために必要なのが「ポートフォリオ(作品集)」です。
ポートフォリオとは、自分の作品を集めた作品集のこと。商品として売られている普通のイラスト集などとは違い、自分のスキルをアピールする目的につくるものです。

ですから、ただ自分の作品を並べるだけではなく、「どのようなスキルがあるのか」「どんな作品が作れるのか」「自分の個性は何か」を企業の人などに伝える「プレゼン資料」として側面があります。
- 原画のラフスケッチ
- 自作したアニメーション作品
- キャラクター設定資料
- 三面図(キャラクターを前、横、後ろの3方向から描いたもの)
- 表情集
- パース図
などを幅広く取り入れ、スキルの幅を見せられるように工夫しましょう。

私たちの学校では、目標の実現につながるポートフォリオの指導にも力を入れており、普段の授業やキャリアセンターで手取り足取りアドバイスしています。また採用先の企業が学校に来て、直接ポートフォリオ指導をしてくれるイベントもあります。
「さっそく自分のポートフォリオをつくってみたい!」という意欲がある方は、ぜひオープンキャンパスの体験授業に参加してください。プロの講師に何でも自由に質問できますので、ポートフォリオづくりについて基本からじっくり教えてもらうことができ、入学前から一歩リードできます!

ステップ3. アニメ制作会社に就職!
ポートフォリオが整ったら、いよいよ就職活動に進みます。アニメ業界では、春〜夏頃に新卒・中途問わず採用が集中する傾向にあります(会社によって異なります)。
就活では、履歴書・自己PR・ポートフォリオ提出のほか、実技課題を出されることもあります。
課題の内容は、動画の作成、キャラ表の模写、オリジナル作画など様々です。また、企業は「この会社の作品が好き」という想いも大切にされることもあるため、志望動機も自己分析して丁寧に書くことがポイントです。
日本デザイナー学院では、就活を成功に導くためのサポート環境が充実していますので、こういった就職課題への取り組み方からエントリーシートの書き方まで、手取り足取り、二人三脚で向き合うことで、毎年安定した就職率を実現しています。
ステップ4. アニメ制作会社に就職する
採用試験を経て内定が決まったら、いよいよアニメーターとしての第一歩です。多くの場合は、まず「動画担当」として現場に入り、一定期間の実務経験を積みます。
この段階では、作業スピードと正確さ、コミュニケーション能力が特に重視されます。さまざまなお仕事をこなしていく中で、現場の経験を通じて、アニメーターとして成長していくための修行期間です。一定の技術レベルに達すると、「原画」や「作画監督」へとステップアップするチャンスもあります。
また就職後には「描く」以外の力、つまりスケジュール管理やチームとのやりとりなどの社会人力も必要になります(どんな業界でも同じですね)。こういった人間としての総合力を身につけるためにも、学生時代には授業やプライベートを含め、アニメ以外のさまざまなことにもチャレンジして、人生経験を積みましょう。
(番外編)個人作家として活動する
近年では、「会社に所属せずにアニメーターとして活動したい」という人も増えてきました。特にSNSやYouTube、pixiv、FANBOXなどを活用し、直接ファンとつながるクリエイターも多く見られます。
『君の名は。』などで知られるアニメ映画監督の新海誠さんも、グラフィックデザイナーとして働くかたわら自主アニメ映画『ほしのこえ』をつくり、商業デビューに至ったエピソードが有名です。
仕事をしていくうちに、ゲームのための映像ではなくて“自分で物語を作りたい”という気持ちが高まっていきました。そこで会社勤めをしながら自主制作でのアニメーション制作を始めたんですが、(中略)そんな気持ちの中で『ほしのこえ』を作り始めました。
語り:新海誠
(参考)Interbelle.inc|アニメーション作家・映画監督 新海 誠
この「個人作家」という道を選ぶ場合、技術力だけでなく「セルフプロデュース力」や「自己管理能力」なども求められることになります。さらに、仕事の依頼や契約関係なども自分で処理する必要があるため、ビジネススキルもある程度必要になってきます。
とはいえ、自分のペースで作品づくりに向き合えたり、自由なスタイルで活動できるのは大きな魅力です。最初は副業として始め、SNSで少しずつファンを増やすところからスタートするのも現実的な手段です。
アニメーターに必要なスキルや、求められる能力
アニメーターには「絵が上手でなければなれない」というイメージを持つ人も多いですが、それだけではありません。確かに描画力は大切ですが、それ以上に「ものを観察する力」や「コツコツ取り組む力」などが重要とされています。ここでは、アニメーターに求められるスキルと、適性について具体的に見ていきましょう。
「動き」の観察力・理解力・表現力
アニメーションとは「動きの再現」ですから、ただ「静止画」を描くこととは異なります。人や動物、風や水など、あらゆる動きの本質を観察し、それを紙やデジタル画面の上で再現する能力が必要になります。
たとえば、人が歩くときの体重移動や肩の揺れ、髪のなびきなど、現実の細かな動きを観察する目があることで、よりリアルで魅力的なアニメーションが可能になります。
この力は訓練によって身につけられるものなので、日々たくさんの物事を観察し、スケッチや模写を繰り返すことで磨くことができます。
粘り強さと継続力
アニメ制作には地道な作業もあり、ひとつの作品が完成するまでには長い工程があります。ワンシーンを仕上げるためにも、何十枚、何百枚という絵を描く必要があります。そのため、根気強くコツコツ作業を続けられたり、そんな作業が好きな人はアニメーターに向いていると言えます。
また、プロの現場では納期厳守が原則なので、絵を描くスピードと正確さの両立も求められます。最初は思うようにできないことも多いかもしれませんが、少しずつ改善し、努力を継続する気持ちを失わないことが何より大切です。
アニメーターになるには、どんな勉強や努力をすればいい?
キャラクターを生きたように動かす、アニメーターの “神ワザ” 。「自分には無理かも?」「特別な才能が必要なんでしょ?」と、アニメーターになれる自信がない人も多いかと思います。
しかしアニメーターは、才能だけですべてが決まる世界ではありません。正しい努力と、そしてアニメへの熱い愛情さえあれば、きっとあなたもアニメーターになることができます。
ここでは、初心者からでもできる具体的な学習方法を紹介します。
デッサン・クロッキーの継続
アニメーションの基本は「観察と描写」。人間の骨格や筋肉の動きを理解したり、現実の風景やモノの動きを再現するため、日常的にデッサンやクロッキーを続けることが大切です。
まずは1日10分くらいからでもいいので毎日続けることで、確実に観察力や表現力が上達していきます。
アニメの模写やトレース
「アニメならではの表現方法」を学ぶには、好きなアニメのシーンを模写したり、トレース(透かし描き)して動きを学ぶ方法も効果的です。動きの「タイミング」「強弱」「間」など、実践からしか学べない感覚を身につけることにもつながります。
ポートフォリオの準備
繰り返しになりますが、アニメーターとしての就職や、またはアニメ作家として仕事を獲得するためには、ポートフォリオ(作品集)でスキルをアピールすることが欠かせません。
作画のトレーニングをするかたわら、その身につけたスキルをアピールできるような作品の制作にも取り組み、ポートフォリオをまとめていく作業もこつこつと続けていきましょう。
最後に:アニメーターを目指す方へ
アニメーターは、決して「天才しかなれない仕事」ではありません。努力と継続、そして「アニメが好き」という情熱さえあれば、誰でも十分にプロを目指せます。
「自分にできるか不安」という人ほど、まずは「知る」ための一歩を踏み出してみてください。
私たち日本デザイナー学院の総合アニメ・デジタルイラスト科では、初心者からプロになるためのカリキュラムと教育環境を整え、お待ちしています。体験授業や説明会、個別相談の機会もご用意していますので、ぜひお気軽にお問合せくださいね。